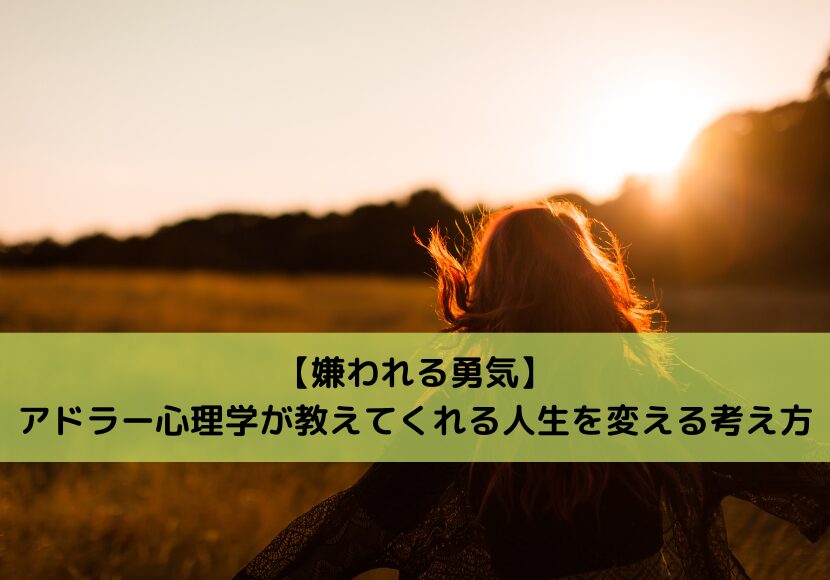人生の考え方を変えてくれるきっかけになってくれた書籍「嫌われる勇気」を紹介します。
Contents
嫌われる勇気
「嫌われる勇気」は、アルフレッド・アドラーの思想に基づいて書かれた書籍です。この本は、2013年に初版が発行されて以来、大きな反響を呼び、多くの読者に支持されています。2017年にはドラマ化もされました。
この書籍では、アドラー心理学の概念を学ぶことができます。書籍の内容としては、哲学者と若い男性の対話形式をとっており、哲学者がアドラー心理学の教えを通じて若者の悩みに答えていく形で展開されていきます。
「嫌われる勇気」は、自己啓発の書籍としてだけではなく、アドラー心理学の入門書ともなっており、自分自身と向き合うためのアドバイスが詰まっています。
私は、2011年に新卒で仕事を始めましたが、一時期、色々と仕事で悩んでしまい、体調を崩してしまうような時期がありました。その時にこの本を読んで大きく考え方が変わり、今では、課長職(マネージャー)になるまで仕事を続けることができています。この本に出合わなければ、どこかでつぶれてしまうこともあったかもしれません。
この記事では、私が本書を通じて感じたことについて紹介したいと思います。
人生の考え方を変えてくれたアドラー心理学
ちょうど新入社員で入社して2年目ぐらいの頃、残業が多く、さらに仕事も何をやってもうまく成果が出せないというような時期がありました。この時期は、心身共につらく、落ち込んだり、あまり寝られなかったりと体調を崩すことが多かったです。
その頃にふと手に取ったのが、この書籍「嫌われる勇気」でした。本書の中で、アドラー心理学について色々と触れられています。すべての考え方を十分理解できたとは思っていませんが、特に中でも私の助けになった考え方が以下です。
- 目的論
- すべての悩みは対人関係
- 課題の分離
以降では、特に上記の点について私が感じたことについて紹介していきたいと思います。
目的を達成する手段として感情が生まれる「目的論」
本書ではいきなり「トラウマは存在しない」というところから始まります。アドラー心理学では、過去の原因に目を向けるのではなく、現在の目的に注目します。
原因に目を向けることを「原因論」、現在の目的に注目することを「目的論」といいます。まとめてみると以下の通りです。アドラー心理学では目的論で物事を考えます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 原因論 | 過去の「原因」があり、結果として現在の感情などが生じる |
| 目的論 | 「目的」が存在し、それを達成する手段として、様々な感情を持ち出している。アドラー心理学ではこちらの考え方をする。 |
トラウマで引きこもっている人は、過去の原因があるのではなく、現在「外に出たくない」という目的を達成するために、不安の感情を作り出しているというのは面白い視点だなと感じました。
他にも、例えばですが、会社の打ち合わせで怒りの感情をぶつけてくる人がいて、嫌な思いをしたことがある人は多いのではないでしょうか。これも、自分の意見を通すという目的のために「怒り」の感情を持ち出しているととらえることができます。
この考え方を知ったところでどうなるかと思うかもしれませんが、私はこの考え方を知ったときに、ものすごく冷静に客観的に周りを見ることができるようになった気がします。
賛否両論ある考え方かもしれませんが、過去の原因で今があるのではなく、すべて何かの目的のためであるというのは、前向きな考え方のように感じていて非常に気に入っています。
すべての悩みは対人関係の悩みであることを理解する
この本では「すべての悩みは対人関係の悩みである」と言っています。
仕事がうまくいかないときは「他人に迷惑がかかる」から悩みます。自分の見た目に自信がないときは「他人がどう自分を評価しているかわからない」から悩みます。このように、すべての悩みは他人がいるから生じるのです。
本書では「劣等感」と「劣等コンプレックス」という言葉を使い分けて説明しています。前者は、自分の求める理想に対して劣っているような感覚で、後者は劣等感を言い訳にしだした状態です。
私が社会人として若いころに体調を崩したのは劣等コンプレックスの状態であったように今になると思います。落ち着いて思い出してみると当時もそれほどできていなかったわけではなく、勝手に周りより劣っていると思い込んでいて、それを言い訳に体調を崩していったように思います。
哲人 健全な劣等感とは、他者との比較のなかで生まれるのではなく、「理想の自分」との比較から生まれるものです。
嫌われる勇気 より引用
書籍内にも、上記のような記載があります。今現在でも、劣等感を感じることは頻繁にありますが、それは理想の自分とのギャップなのだととらえて、他の人と比べないようにしています。
とはいえ、簡単ではなく、劣等コンプレックスのような状態に陥りそうなこともあり、そのようなときにはこの考え方を思い出すようにしています。
「課題の分離」により人生が楽になる
私が「嫌われる勇気」の中で一番好きな考え方は「課題の分離」です。
課題の分離とは、自分の課題と他人の課題を明確に分け、他人の課題には踏み込まないようにするという考え方です。
われわれは「これは誰の課題なのか?」という視点から、自分の課題と他者の課題とを分離していく必要があるのです。
嫌われる勇気 より引用
課題を見分ける方法は「ある選択をしたときに結果を引き受け、責任を取るのは誰か」を考えることです。
私が若いころに体調を崩したときは、自分の責任範囲ではないことでもなんでも自分でできないといけないと考えてしまい、自分の許容できる限界を超えてしまったのだと、今では思っています。
現在では、自分の課題と他者の課題を分けるように考えるように意識しています。こちらもなかなか難しく、そんなに簡単にできるものではありません。ただし、この考え方を中心に考えるようになってから不必要にストレスと感じることはなくなったように思います。
「課題の分離」について理解・共感していない人に対して、あまりこの主張を押し付けると反発されるかもしれませんので注意してください。以前、他部署とのやり取りに関することでこの考え方の話をしたら、当時の上司には「その考え方は好きではない」と反発されました。
私自身はこの考え方を基本に考えていますが、他の人にはその人の考え方があるので押し付けないようにした方がいいかもしれません。これも課題の分離の一つですね。
まとめ
私の人生の考え方に大きな影響を与えてくれた書籍「嫌われる勇気」について紹介しました。
この本の中でも特に私が気に入っている「目的論」「すべての悩みは対人関係」「課題の分離」という内容についてピックアップして感じたことなどを紹介しました。
アドラー心理学は、分かったような気になってもなかなか実践は難しいものだなと感じます。ただ、アドラー心理学の考え方を参考にすることで生きていく中で気持ちが楽になる部分があったなというのが個人的な感想です。これからも、私の中の基本的な考え方の一つとなっていくだろうなと思っています。
自分の軸となるような考え方の一つを提供してくれた本書にはとても感謝しています。少しでも気になった方は手に取って読んでみていただきたいなと思います。